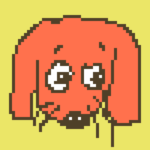「今日の面談、うまくいくかな…」
保育士の皆さんにとって、保護者面談は少し緊張するイベントかもしれませんね。
限られた時間の中で、子どもの成長を伝え、保護者の疑問や不安に寄り添わなければならない。
準備に時間をかけ、頭の中で話す内容をシミュレーションしても、実際に保護者を目の前にすると、どうしても一方的な報告になってしまう…そんな経験はありませんか?
もしかしたら、それはあなただけではないかもしれません。
多くの保育士さんが、保護者面談で「保育士の意見ばかり」を伝えてしまい、後で「もっと保護者の話を聞けばよかった…」と反省することがあるようです。
でも、ちょっと待ってください!保護者面談は、本来、保育士と保護者が手を取り合い、お子さんの成長を一緒に見守るための大切な機会のはず。
一方通行のコミュニケーションでは、その貴重な機会を十分に活かすことができません。
この記事では、保護者の気持ちに寄り添い、より実りある保護者面談にするための具体的な方法を、じっくりとご紹介します。
面談への苦手意識を少しでも軽くし、保護者との信頼関係を深めるための一歩を踏み出してみませんか?
なぜ「保育士の意見ばかり」の伝え方が逆効果なのか?【元保育士の経験から】
想像してみてください。
あなたが、自分の仕事について一方的に報告を受けるだけの場面を。
質問をする隙もなく、ただ話を聞いているだけで、自分の意見や疑問は全く聞いてもらえないとしたら、どんな気持ちになるでしょうか?
保護者の方も同じです。面談という限られた時間の中で、保育士から子どもの園での様子や成長について聞きたいと思っていますが、それ以上に、自分の子どもがどう思っているのか、どんなことに悩んでいるのか、そして、保育士に何を期待しているのかを知りたいと考えているのです。
保育士が一方的に話してしまうと、保護者の期待は満たされず、以下のようなデメリットが生じる可能性があります。
『保護者の不安や疑問が解消されない』
「うちの子、園で本当に楽しんでいるのかな?」「何か困っていることはないのかな?」といった保護者の根源的な不安は、一方的な報告では解消されません。
『保育士への不信感につながる』
「結局、先生は自分の言いたいことだけ言っているんだな…」と感じさせてしまい、保育士への信頼を損なう可能性があります。
『家庭と園の連携がうまくいかない』
お互いの状況や考えを理解し合えないため、子どもの成長をサポートするための連携がスムーズに進まなくなります。
『結果的に、子どもの成長を阻害する可能性も』
保護者が園に対して不信感を抱いていると、それが子どもにも伝わり、園生活への不安につながることもあります。
例えば、こんなケースを考えてみましょう。
例①「友達とのトラブルについて・・」
例②『スマホの使用の話になって・・・』
上記のような例では、保育士は事実を伝えていますが、保護者の気持ちや背景にある疑問には全く触れていません。
保護者は、子どもの行動の原因や、保育士がどのように対応しているのかを知りたいと思っているかもしれません。一方的な伝え方では、保護者の不安は募るばかりです。
私は、面談で保護者の話に耳を傾けることで、子どもの園での様子だけでなく、保護者の方が抱える様々な悩みに気づきました。育児の悩みはもちろん、仕事との両立、家事の負担、そして経済的な不安など、保護者の方を取り巻く状況は複雑です。
特に、ワンオペ育児で誰にも頼ることができず、孤独感や疲労感を感じている保護者の方も少なくありません。
面談は、そうした保護者の方の苦悩に寄り添い、励ますことで、深い信頼関係を築く貴重な機会になるよう心がけてました。
保護者面談は、保育士が一方的に評価を下す場ではなく、保護者と保育士が協力して子どもの成長をサポートするための対話の場であるべきなのです。そして、その対話を通じて、保育士は保護者支援という重要な役割を担うことができるのです。
保護者の気持ちを汲み取るために大切なこと

では、保護者の気持ちを汲み取り、より良い対話をするためには、具体的にどのようなことを意識すれば良いのでしょうか?
聞く姿勢をアップデートする
「聞く」と「聴く」は違います。ただ耳で音を捉えるのではなく、相手の言葉に心を傾け、真意を理解しようとするのが「聴く」です。
保護者の話を「聴く」ためには、以下の点を意識してみましょう。
・目を見て、うなずきながら聴く
相手に「あなたの話をきちんと聞いていますよ」というメッセージが伝わります。
・話を遮らず、最後まで聴く
途中で口を挟みたくなる気持ちを抑え、最後まで相手の話に耳を傾けましょう。
・メモを取りながら聴くのも効果的:
重要なポイントをメモすることで、後で内容を整理しやすくなりますし、保護者にも真剣に聞いている姿勢が伝わります。
・言葉の裏にある気持ちを想像する
保護者が言葉にしないけれど、心配していることはないか?困っていることはないか?どんな情報を求めているのか?想像力を働かせることが大切です。
質問力を磨く
質問は、保護者の考えや気持ちを引き出すための強力なツールです。効果的な質問をすることで、より深いコミュニケーションが可能になります。
・YES/NOで終わらない質問〜「オープンクエスチョン」を活用しよう〜
「はい」「いいえ」で答えられる質問ではなく、「最近、お子さんのことで気になることはありますか?」「ご家庭では、お子さんはどんな様子ですか?」のように、保護者が自由に答えられる質問を意識しましょう。
・具体的なエピソードを引き出す質問
「〇〇な時、お子さんはどんな反応をしますか?」「何かきっかけはありましたか?」のように、具体的な状況や行動について尋ねることで、より詳しい情報を得ることができます。
・保護者の状況に配慮した質問をする
例えば、「最近、お疲れではないですか?」「何かお手伝いできることはありますか?」といった質問は、保護者の心を開き、悩みを打ち明けてもらいやすくなります。
・質問を通して、保護者の価値観や子育て観を知る:
保護者がどのようなことを大切に考えているのか、どんな子育てをしたいと思っているのかを知ることは、その後の関わり方にも大きく影響します。
共感力を高める
共感は、相手の気持ちに寄り添い、理解しようとする姿勢です。保護者の気持ちに共感することで、信頼関係を築きやすくなります。
・「〇〇なのですね」「大変でしたね」共感の言葉を意識する:
保護者の話に対して、安易な励ましではなく、気持ちを受け止める言葉を意識的に使いましょう。
・頭ごなしに否定しない。「そうなんですね」とまずは受け止める
保護者の意見や考えが自分と違っていても、まずは受け止め、否定的な言葉は避けるようにしましょう。
・保護者の感情に寄り添う言葉を選ぶ
保護者が悲しそうに話している時は、「辛かったですね」、困っているように話している時は、「何かお困りですか?」など、相手の感情に合わせた言葉を選ぶことが大切です。
言葉を「翻訳」する
保護者の言葉をそのまま受け取るだけでなく、その言葉の裏にある意味を理解しようとすることも重要です。
・保護者の言葉を要約して確認する
保護者の話を自分の言葉で要約し、認識に間違いがないか確認することで、誤解を防ぎます。
・認識のずれを防ぐ
曖昧な部分や不明な点は、遠慮せずに確認しましょう。
具体的な伝え方のポイント
〜保護者との「キャッチボール」を意識する〜
保護者面談を一方通行で終わらせないためには、保育士からの一方的な説明ではなく、保護者との間でしっかりと「キャッチボール」をすることが大切です。
・ポジティブな情報から始める:
面談の冒頭は、お子さんの成長や良い変化など、ポジティブな話題から入るように心がけましょう。
「〇〇さんは、最近お友達と積極的に遊ぶようになりました」「以前は人見知りする様子もありましたが、最近は笑顔を見せてくれることが増えました」など、具体的なエピソードを交えると、保護者は安心し、その後の話も聞きやすくなります。
・課題や心配事を伝える時は「サンドイッチ話法」:
もし、お子さんの発達や行動について気になる点がある場合は、最初にポジティブな情報を伝え、その後に課題を伝え、最後にまたポジティブな情報で締めくくる「サンドイッチ話法」が有効です。
例えば、「〇〇さんは、粘り強く活動に取り組むことができるようになりました。一方で、集中が途切れてしまう場面も見られます。ご家庭ではいかがですか?〇〇さんの頑張りを、これからも一緒に見守っていきたいと思っています」のように伝えると、保護者は冷静に話を聞きやすくなります。
頭ごなしな指摘は避け、「〇〇な点が少し気になっています」といった柔らかい表現を心がけましょう。
・園の状況や方針を伝える時は「なぜ?」を意識する
園のルールや行事について説明する際は、「〇〇にご協力をお願いします」と一方的に伝えるのではなく、「なぜ、それが必要なのか」という背景や理由を丁寧に説明することが大切です。
例えば、アレルギー対応について説明する際は、「お子さんの安全を守るために、〇〇のような対応をさせていただいています」と理由を添えることで、保護者の理解と協力を得やすくなります。また、保護者からの疑問や質問には、丁寧に答えるようにしましょう。
・保護者の状況に合わせた伝え方を心がける
例えば、時間に余裕がない保護者の方には、要点をまとめて簡潔に伝える、忙しい保護者の方には、後日メールなどで情報を共有するなど、柔軟な対応も検討しましょう。
・言葉選びは慎重に:
否定的な言葉や断定的な言葉は避け、クッション言葉(「少し」「~かもしれませんが」「~のように見えます」など)を活用するなど、言葉遣いに配慮しましょう。
保護者の状況や気持ちに配慮した言葉を選ぶことが、良好な関係を築く上で非常に重要です。
面談後も関係性を育む〜保護者支援の継続〜

保護者面談は、一度きりのイベントではありません。
面談で得られた保護者の情報やニーズを踏まえ、継続的な保護者支援につなげていくことが大切です。
・面談内容の簡単なまとめを共有する(必要に応じて)
面談で話した内容の重要なポイントを簡単にまとめ、保護者に共有することで、認識のずれを防ぎ、安心感を与えることができます。
・家庭との連携を継続する姿勢を見せる
面談で話し合った内容を踏まえ、家庭と園で連携して取り組むべきことがあれば、積極的に情報共有を行いましょう。「何かご家庭でできることがあれば、遠慮なくおっしゃってください」といった言葉かけも大切です。
・園として提供できるサポートを積極的に伝える
一時預かり、延長保育、育児相談など、園が提供できるサポートがあれば、面談の際に改めて伝え、利用を促すことも保護者支援の一環となります。
・地域の支援情報を共有する
地域の子育て支援センターや相談窓口など、園外の情報を共有することも、保護者の方の助けになることがあります。
・次回の面談につなげる言葉かけをする
面談の最後に、「今日お話できてよかったです。今後も何かあれば遠慮なくご連絡ください」「次回の面談で、またお子さんの成長についてお話できるのを楽しみにしています」といった言葉を添えることで、今後の関係性も良好に保てます。
【まとめ】保護者と保育士は「チーム」
~面談は保護者支援の第一歩~
保護者面談は、保護者と保育士がそれぞれの立場から子どもの成長を考え、協力し合うための貴重な時間です。
一方通行のコミュニケーションではなく、お互いの気持ちを理解し、尊重し合うことで、より深い信頼関係を築くことができます。
保護者の気持ちに寄り添うことは、決して簡単なことではありません。しかし、今回ご紹介したポイントを意識することで、少しずつ変化を感じられるはずです。
面談を「怖いもの」「大変なもの」ではなく、「保護者とじっくり話せる貴重な時間」と捉え、積極的にコミュニケーションを取ってみてください。
そして、面談で得られた情報を活かし、継続的な保護者支援につなげていくことこそ、保護者と保育士が「チーム」となり、手を取り合って子どもの成長をサポートしていく上で、何よりも大切なのです。