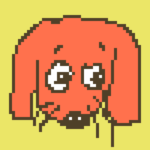保育士として長年、多くの子どもの発達と成長を支援する中で、子どもたちへの「関わり」は、その発達を支える上で欠かせない重要な要素だと痛感してまいりました。
単に注意するのではなく、一人ひとりの発達段階や個性、置かれた状況を丁寧に理解し、適切な言葉と態度で接することが、子どもの主体的な成長を促す丁寧な関わりだと信じています。
今回は、私の経験をもとに、未満児と以上児それぞれの発達段階に合わせた、より分かりやすく効果的な関わり方について考えていきましょう。
子どもたちの育ちをサポートするために
 私たちが保育の現場で子どもたちと関わるのは、ただ「ダメ!」と行動を直すだけではありません。
私たちが保育の現場で子どもたちと関わるのは、ただ「ダメ!」と行動を直すだけではありません。
子どもたちが、友達と仲良くしたり、みんなで決めたルールを守ったり、自分で考えて行動できるようになる力を、じっくりと育んでいくこと。
そのためには、一人ひとりの成長段階をしっかりと理解して、その子に合った温かい関わりを大切にすることが、子どもたちの自信を育み、お友達との良い関係を築きながら成長していく上で、何よりも大切なんです。
未満児(0~3歳)への関わり方『言葉よりも安心できる関係を』
まだ言葉での複雑なコミュニケーションが難しい未満児には、不適切な行動をすぐに止めるとともに、情緒的な安定を図ることが重要です。
未満児の発達段階と特徴
・認知発達
単語や短い言葉は理解できますが、長い話や難しいことはまだ分かりません。
・情意発達
自分の気持ちを直接的な行動で表し、自分でコントロールするのは難しいです。
・探索行動
周りのものに興味があり、触ったり、なめたりして学びます。
・愛着形成
特定の保育者との安定した関係が、心の安定につながります。
具体的な関わりのポイント
・短く具体的な言葉で伝える
「だめだよ」「こちらへどうぞ」など、短い言葉で、してほしくないことを伝えます。
・行動と気持ちを分けて考える
例えば、友達を噛んだ子には、「噛むのは痛いよ」と行動を伝えつつ、「〇〇ちゃんも遊びたかったんだね」と気持ちに寄り添います。
・優しい声と身体的な触れ合い
穏やかな声で話しかけ、抱っこなどで安心感を与えます。
・危険な行為はすぐに止める
安全を守るため、「あぶない!」と強く伝え、すぐに安全な場所に移動させます。
・落ち着いて関係を再び作る
行動を止めた後も、優しく接することで、子どもとの信頼関係を保ちます。
気をつけること
・感情的に叱らない
大声は子どもを不安にさせます。落ち着いて対応しましょう。
・体罰は絶対にしない
子どもの心と体に傷を残し、信頼を失います。
・「悪い子」などの言葉を使わない
子どもの自信をなくすような言葉は避けましょう。
・長い時間叱らない
まだ集中力が続かないため、短い時間で伝えましょう。
以上児(4~6歳)への関わり方『理由を理解させ自分で考える力を』
言葉が発達し、社会性も身についてくる以上児には、なぜその行動がいけないのかを理解させ、自分で考えて行動できるようになるための関わりが大切です。
以上児の発達段階と特徴
・認知発達
物事の理由や結果を理解できるようになります。
・社会性の発達
友達との関わりを通して、ルールや我慢を学びます。
・道徳性の芽生え
良いことと悪いことの区別がつき始めます
・自我意識の発達
自分の意見を持つようになり、周りの意見と折り合いをつけることを学びます。
具体的な関わりのポイント
・行動の理由と結果を説明する
「お友達のおもちゃを無理に取ると、〇〇くんは悲しい気持ちになるよ。みんなで楽しく遊ぶためには、どうしたらよかったかな?」のように、具体的に問いかけます。
・気持ちに寄り添いながら話す
「〇〇ちゃんがそのおもちゃで遊びたかった気持ちはわかるけれど、順番を守ってみんなで使う方が、もっと楽しく遊べると思わない?」のように、共感を示します。
・どうすればよかったのかを一緒に考える
「もし△△のおもちゃで遊びたい時は、『貸して』って優しく言ってみるのはどうかな?」のように、具体的な方法を提案します。
・いけないことと、どうすればいいかを明確に伝える
例えば、お友達を身体的に傷つけてしまった場合には、「なんでお友達を叩いたの? 何か嫌なことがあったかな?」と気持ちを丁寧に聞き、「嫌な思いをしたかもしれないけど、叩かずに言葉で伝えたら、二人とも仲良く遊べたかもしれないね! お友達には謝れるかな?」と促し、関係修復に向けた具体的な行動を促します。
気をつけること
・他の子どもと比べない
一人ひとりの成長は違うため、比較は避けましょう。
・過去の失敗を持ち出さない
今の行動に焦点を当てて関わりましょう。
・頭ごなしに否定しない
子どもの言い分も聞き、理由を説明しましょう。
・みんなの前で強く叱らない
子どもの自己評価を傷つける可能性があります。
体験談〜発達段階に合わせた関わりで見られた変化〜
2歳児クラスで、Aちゃんがお友達のおもちゃを「貸して」と言えずに、おもちゃの取り合いを始めました。
その時、お友達ともみ合いになり、Aちゃんはお友達を噛んでしまったのです。
私はすぐにAちゃんの体を優しく抱きしめ、「〇〇ちゃん(噛まれたお友達)が『痛いよ』って言っているね。お友達は痛そうでしょ・・・」と、落ち着いた声(低い声)で伝えました。
Aちゃんをそっと抱きしめながら、「今度は、遊びたいおもちゃがあったら、『かして』って言ってみようね」と、具体的な言葉を教えました。
数日後、Aちゃんが別のおもちゃを欲しがった時、少しドキドキしながらも「かして」と言うことができました。
お友達が笑顔で「いいよ」と貸してくれた時、私はすぐにAちゃんの「貸してって言えたね。」とたくさん褒めました。
この経験から、言葉がまだ十分に発達していない子どもには、衝動的な行動をすぐに止め、安心できる温かい雰囲気の中で、具体的な代替行動を丁寧に伝えることが、とても大切だと改めて感じました。
5歳児クラスのB君が、友達が大切にしている制作物を壊してしまった時、私はB君を個別のスペースに呼び、「どうして壊してしまったのか、理由を聞かせてください」と尋ねました。
B君は、自分の気持ちをうまく言えずにいました。
私は彼の気持ちを受け止めながら、「自分の思いを伝えることは大切だけど、人の物を壊すのは悲しいことだよ。もし困ったことがあったら、先生に教えてね」と伝えました。
その後、B君は友達に「ごめんね」と謝ることができました。
言葉で理由を理解できる年齢には、気持ちを受け止めながら、適切な行動を促すことが大切だと学びました。
関わった後のフォローアップ
〜関係を再び温かくにし、学びを深める〜
関わった後は、子どもの気持ちを注意深く見守り、安心できる言葉をかけてあげましょう。「〇〇ちゃんのことは、ずっと大切に思っているよ」と伝え、再び安心させてあげます。「次はどうすればもっとうまくできるかな?」と、一緒に考えることも、子どもの成長につながります。
年齢別の関わりで大切なこと
| 年齢 | 関わりのポイント | フォローアップで大切にしたいこと |
|---|---|---|
| 0~3歳 | すぐに止める、安心させる、具体的な言葉 | 身体的な触れ合いで安心感を再び与える |
| 4~6歳 | 理由を説明する、気持ちに寄り添う、一緒に考える | 頑張りを認め、次のステップへの期待を伝える |
結論「一人ひとりの成長に合わせた丁寧な関わりを」
保育士としての経験を通して、子どもの発達段階を丁寧に理解し、それぞれの特性に合わせた適切な関わりを行うことが、子どもたちの健やかな成長を支える上で本当に大切だと感じています。
この情報が、日々の保育実践において、少しでもお役に立てれば幸いです。